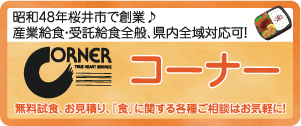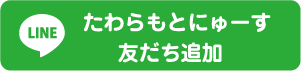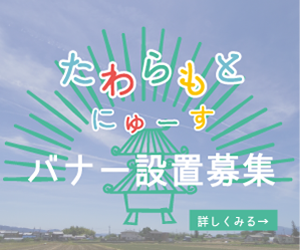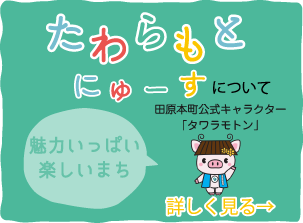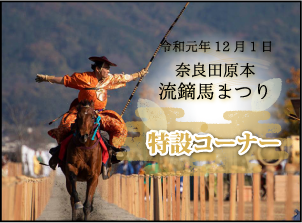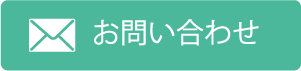~ボランティアガイドTさんより~
この田原本町に、「田原本藩平野家陣屋」があったのを知っていますか⁉
1582年織田信長の死後、柴田勝家と豊臣秀吉が覇権を争い、近江国伊香郡(現:滋賀県長浜市)で起きた賤ケ岳の合戦で、武功をあげた平野長泰は、秀吉から褒賞として大和国十市郡内(田原本、佐味、竹田、薬王寺、橿原市飯高町の一部)五千石の領地もらいました。
しかし初代長泰さん、「権兵衛」と呼ばれる豪放な人で、自分は京都の伏見に住み,田原本には陣屋を置かず、浄土真宗の教行寺に支配を任せ「寺内町(じないちょう、じないまち)」が造られていきました。
そして、2代目平野長勝さんは、田原本を支配するため、教行寺の作った寺内町の東部の寺川べりに「陣屋」を作ったのです。陣屋の西には大和の幹線道路・中街道が通り、寺内町とつながり(新たに街を作らなくてよく)、交通、経済の中心として発達していきました。そして、「大和の大阪」といわれるように、たくさんの人々がこの田原本にやってきました。その道沿いに立つ石の道標(みちしるべ)は当時の名残です。
又、教行寺はその後、箸尾に移転し、跡地に本誓寺(ほんせいじ・浄土宗)と浄照寺(じょうしょうじ・浄土真宗)の二つの寺が建てられました。
平野家は、旗本ですが長泰の旧功の経歴から大名に準ずる待遇を与えられ、交替寄合衆として参勤交代も務め、1595年~1871年までの280年間10代にわたり続きました。
廃藩置県で田原本藩は歴史の幕を閉じ、明治19年その跡地に田原本尋常小学校が建てられました。その後、今の町役場が建てられました。
<寺内町おまけ>石の話
「道沿いに置かれた道標」のお話です!!
皆さん!石の道標の中には『すぐ』という文字が書かれたものがあります。
この『すぐ』は、「すぐそこですよ」のことではなく、「この道をまっすぐ進んで下さい」のことです!!
町巡りの際に、道標にも注目してみてくださいね。
ーーーーー
2/24(日・祝)「たわらもと歴史講座」開催!
/
テーマは「平野長泰と田原本」
\
13時から当日受付となります。(開演14時、定員120名、参加費700円)
豊臣秀吉との関わりや弟・秀長の治めた大和郡山との比較もありますので、今話題の2026年度NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の理解にもつながる内容です。
ぜひ、ご参加ください。お待ちしております😊
■特設ページ
https://tawaramoton.com/r6rekishi/